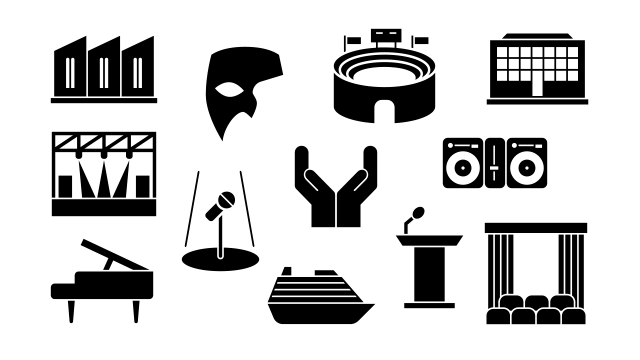『セールスマンの死』に新しい息吹を与えたd&b Soundscape。
d&b Soundscapeが劇場分野で画期的な発展を見せ続ける中、ウエストエンドで行われたこの公演は、舞台芸術の劇作法におけるサウンドの重要性を提示し、そしてサウンドが制作において新しい意味を持つという時代に突入したことを世界に見せつけました。
昨年末、ロンドンのウエストエンドで上演されたアーサー・ミラーのピューリッツァー賞受賞作『セールスマンの死』は、最新の本格派演劇として脚光を浴びることになりました。ピカデリー劇場で披露され、称賛を受けた前作『リーマン・トリロジー』と同様、このパワフルな作品『セールスマンの死』でも、革新的なd&bSoundscapeが重要な創造的役割を担うことになりました。
「マリアンヌ・エリオットが『リーマン・トリロジー』で観客としてそのサウンドを体験した後に、私にこのシステムの話を持ちかけてきたのです。(今回初めて「Soundscapeデザイナー」という役職で表記された)ドミニク・ビルキー氏は、この舞台の二人の監督のうちの一人(もう一人の監督はミランダ・クロムウェル氏)である。「観客に気づかれることなく、ボーカルを補強できることに感心したようでした」とその経緯を語りましす。
ビルキー氏は「Soundscapeデザイナー」として、同プロダクションのサウンドデザイナー、キャロライン・ダウニング氏と一緒に仕事をすることになりました。
ビルキー氏は、国立劇団の『リーマン・トリロジー』の上演でSoundscapeの導入を成功にさせた人物でもあり、Soundscapeの潜在能力をさらに引き出していくことに大変興味があったと言います。「Soundscapeを使うたびに、その訴求力や柔軟性、クリエイティブに使える点に感心させられます。両制作でのSoundscapeの違いは、ワークフローが効率的になった点と、d&bチームがプログラミングとシステム機能に関してシステムの実行速度を格段に向上させてくれた点です」とビルキー氏。
「この作品の狙いは、回転するガラス の立方体に対処する必要がないということから、リーマンの場合とは少し異なっていました」とビルキー氏は言います。「『セールスマンの死』の観客は、常に出演者から主な音声を聴くことができますが、リーマンの場合はそうではありませんでした」
ディレイとして、2階席には8本のE6と8本のE5が、1階席には8本の16Cコラムラウドスピーカーと8本のE5が使用されました。フロントシステムは10本のY10Pと5本のY7Pをトラスに設置して、1階席、2階席、バルコニーをカバーし、ステージ前方の12本のE4で(『リーマン・トリロジー』では8本の16C)フロントフィルを追加的にサポートしました。2階席上部には単一ディレイラインとしてT10ラウドスピーカーを水平方向にPoint Sourceモードで配置し、サラウンドは主にE5(一階席に16本、2階席に12本、バルコニーに8本)で構成し、それを一組のE8がサポートしました。
サブ・リインフォースメントとして、フライングしたV-SUB 2本とグランドスタックしたB6 SUB 2本を使用し、ステージ上には、E8が2本、E6が6本、E4が3本、B2 SUBが1本。このシステムは、8本のDS10 AESブリッジ経由で2台の DS100シグナルエンジン(カスケード方式)からフィードされ、26台のD20アンプと2台のD80アンプが増幅を担いました。今回も『リーマン・トリロジー』と同様、音響機材はすべてStage Sound Services社のフィル・ハーリー氏と彼のチームが供給しました。
「リーマンでの経験から、今回の制作ではDS100の制御方法を変えました」とビルキー氏は付け加えます。「パフォーマンスの性質が異なるため、QLabを使用してユニットを直接制御することを選択し、これにより、編集や技術プロセスでもっと柔軟に対応することができるようになりました」。また、ステージ上のラウドスピーカーにも手が加えられました。
ビルキー氏は、新しいワークフローのおかげで他のクリエイター達とサウンドに関してもっと話をできるようになったと言います。「今では共通言語があるので、以前はビジュアルアート関係の人たちだけがしていたようなディスカッションに誰でも参加できるようになりました」。
d&b Soundscapeのテクノロジーは、劇場のサウンドデザインの役割や見方を、驚くほど変えることになったのです。これまでは技術専門家のものとしか考えられていなかった劇場のサウンドデザインという分野ですが、これは演出や照明、セットと同様に、観客に大きな影響を与えるものなので、洗練された創造的な芸術分野として位置づけできることに議論の余地はないでしょう。