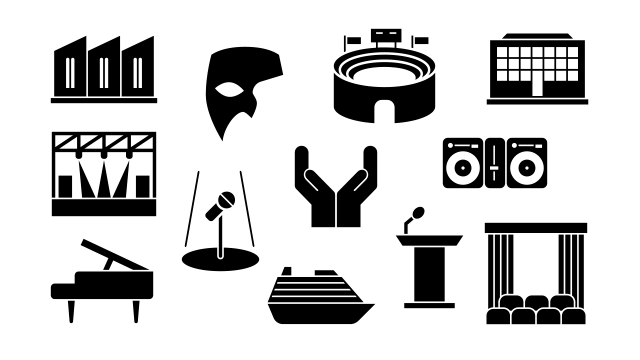Coldplayのホットなツアーとホットなサウンド。
フランス革命に関する暗示が効果的に反映され、そして英雄的資質と人間の意識の激しい融合の意図は、様々なバンドがジャケットに表現したいことです。ColdplayのワールドツアーはBonoのようなビート感とは異なると思いますが、彼らは彼らなりのメッセージの伝達方法を持っていると思われるものです。衣装はキュロットスカートですが、言葉は深く、そして鋭い物を含んでいます。 それらのメッセージの伝達はFOHエンジニアのDaniel Green氏の仕事であり課題でもあります。「私は主に彼らの音楽の中に空間的感覚を模索しています。」と彼は1995年のインタビューで語っています。「リバーブやディレイを多様して空間を作りますが、特にボーカルにかけるリバーブが重要です。」そのようにして拡張された声は彼がツアーで使用しているd&b audiotechnikのJ-Seriesより聴こえてきます。これは前のツアーで使用していたシステムから変更された物ですが、変更に当たっては時間を掛けて慎重に考慮されたということです。「Wigwam社は我々に2つのシステムの聴き比べを提供してくれました。前のツアーで使用したシステムとd&bのJ-Series。これをLite Structuresという大きなリハーサルスペースで比較できたので理想的とも言える試聴になりました。 Digidesign社のVenueをいつも使用しているのでそこにあった同じものを使用したのでより実際に近い状態で比較することができました。」そしてGreen氏と彼のシステムエンジニアTony Smith氏はd&bを使用する決断を下しました。「抽象的な表現になりますが、 J-Seriesの方がよりロックしてる感じでした。」とGreen氏。「ステレオ感が広く感じられ、システム性能もJの方がより精細まで表現してくれる感じです。サブウーファーは絶対的にd&bの方が優れていました。」 Smith氏はGreen氏の選択に同意した上で更に詳細に言及します。「私は昨年行われたジョージマイケルのスタジアムショーでJ-Seriesを使用したことがありました。」このツアーは音に関してヨーロッパの有名な新聞各紙で絶賛されたWigwam社の過去絶賛を受けた仕事の一つです。「システムは非常に簡単で吊り上げて音を出すだけで良いのです。」とSmith氏。「そのような観点からColdplayに使用することに何の抵抗もありませんでした。」 チケットのニーズを考えた場合どうしても会場が大きくなります。「大きなアリーナでは客席が270度、ほぼステージを囲む様に設置されるためメイン、サイド、リアの各所に2か所づつフライングアレイをを設置しました。」とSmith氏。「メインシステムの横には6台のJサブウーファーが吊ってあります。 J-SUBに関してはDan氏と全く同意見でこのようなサブウーファーは今まで見たことが無いという感じです。ニアフィル用にはステージを囲むようにd&bのQ10とQ7を配置し、4台のB2-SUBのグランドスタックも設置しINFRAモードで駆動して低域を拡張しています。」広大なエリアをカバーするシステムのコントロールに Smith氏はd&b R1リモートコントロールソフトウェアを使用しています。 一方のGreen氏の課題はそれらのシステムを通して届けられる音です。「ステージ上は特に変わった部分はなく、ギターにShure SM57、ボーカルにShureのSM58ワイアレス、タムに421といったような普通のものです。」ドラマーのWill Champion氏は激しく叩くことで有名です。「その通りで必然的にChrisのマイクへのドラムのかぶりこみが多いので上げたり下げたりに時間をかけています。しかし彼らの曲を熟知しているため曲のどの部分で何をしなくてはいけないかが良く分かっているので大したことではありません。」 Green氏はバンドのスピリットや本質を極めて良く捕えています。もし皆さんがColdplayの革命をご覧になったのであれば8月のアメリカはEighth Day Sound社によるサービス、その後のヨーロッパでのフェス、スタジアム、アリーナツアーは再度Wigwam社によって提供されたサービスでした。そして最終は地元に戻って9月18、19日にウェンブリースタジアムで行われました。